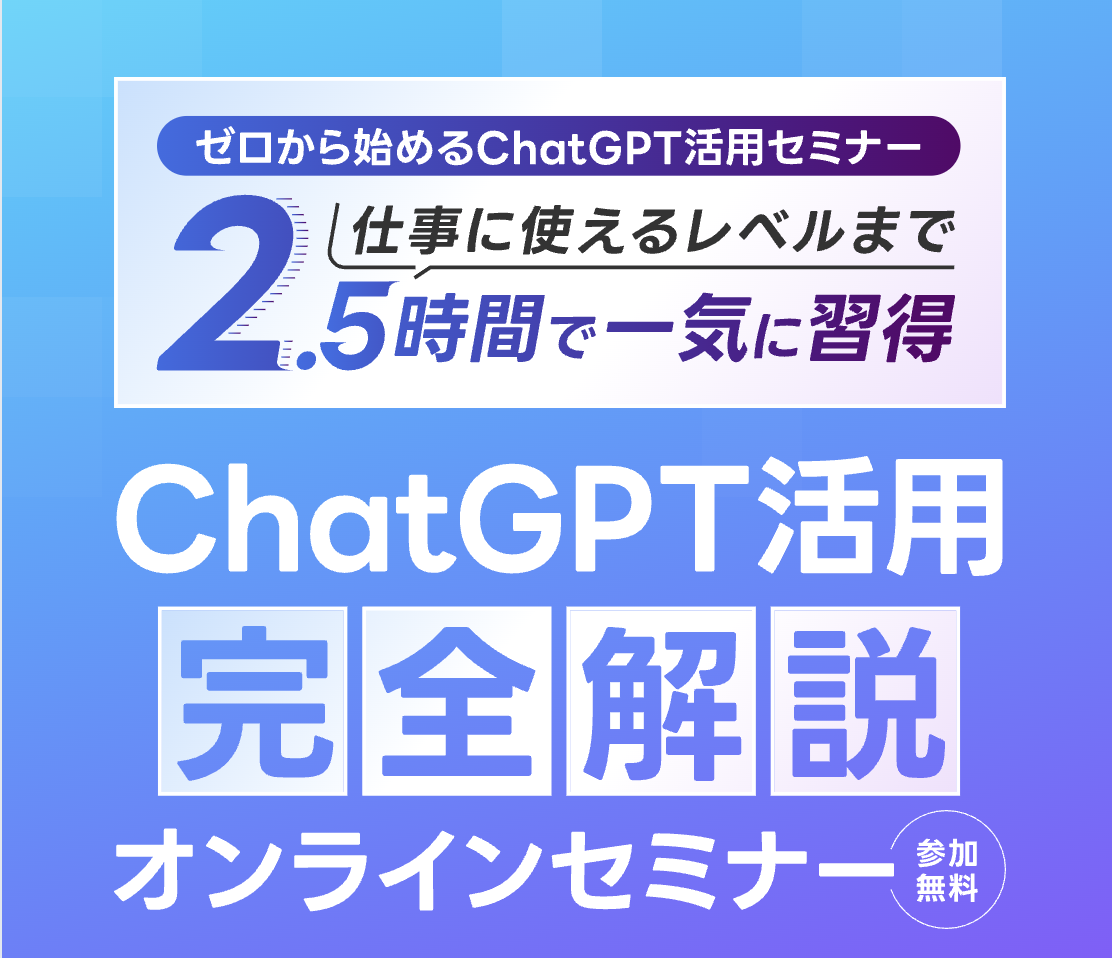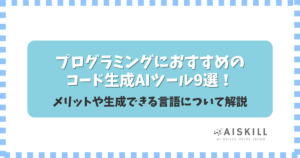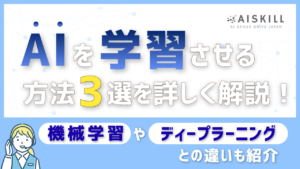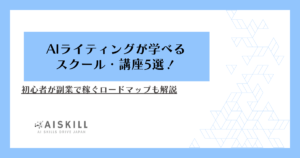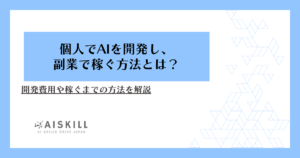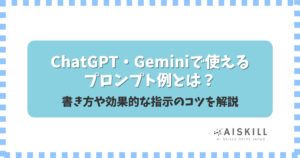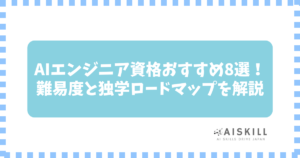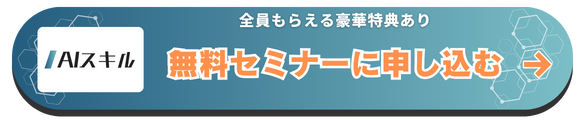AI活用の広がりとともに、「G検定(ジェネラリスト検定)」への関心が高まっています。
しかし、「実際の難易度はどれくらいか」「文系で数学が苦手でも合格できるのか」といった不安や疑問を持つ方も少なくありません。
この記事では、G検定の難易度を最新の合格率、必要な勉強時間、E資格やDS検定など他資格との比較を交えて多角的に解説します。
『AIスキルアカデミー』
- ゼロから始めるChatGTP活用セミナー
- 実用レベルまで2.5時間で一気に取得
- セミナー参加で豪華特典配布
- 初心者でもわかるプロンプト作成方法
- よくある疑問を実例で解決
\AI副業で稼ぐためのロードマップをプレゼント!/
G検定(ジェネラリスト検定)とは?
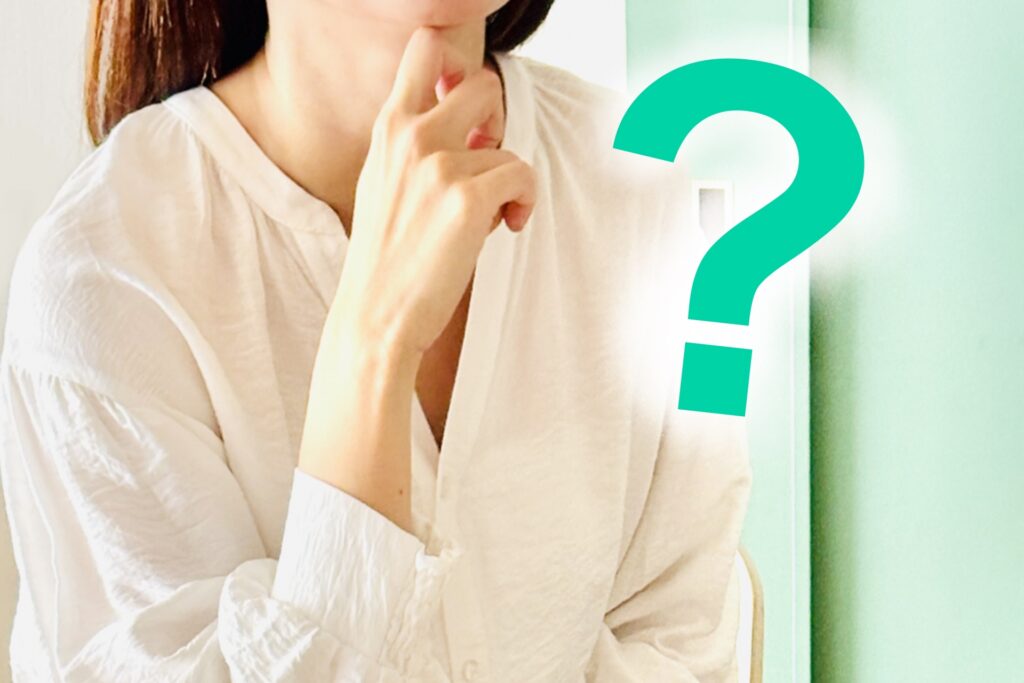
G検定の難易度を理解する前提として、まずは試験の基本的な概要を知りましょう。
G検定は、通称「ジェネラリスト検定」と呼ばれ、一般社団法人日本ディープラーニング協会(JDLA)が主催する、AI・ディープラーニングの基礎知識や活用リテラシーを問う資格試験のことです。
AIをビジネスに活用する「ジェネラリスト」人材の育成を目的としており、エンジニアだけでなく、企画職や営業職、管理職など、幅広い層の受験者が増えています。
受験概要
G検定の基本的な試験概要は以下の通りです。
試験はオンライン形式(IBT)で実施され、自宅や職場のPCから受験が可能です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 試験時間 | 120分 |
| 出題形式 | 多肢選択式(知識問題) |
| 問題数 | 160問程度 |
| 受験資格 | 制限なし |
| 受験方法 | オンライン実施(自宅受験) |
| 受験料(一般) | 13,200円(税込) |
| 受験料(学生) | 5,500円(税込) |
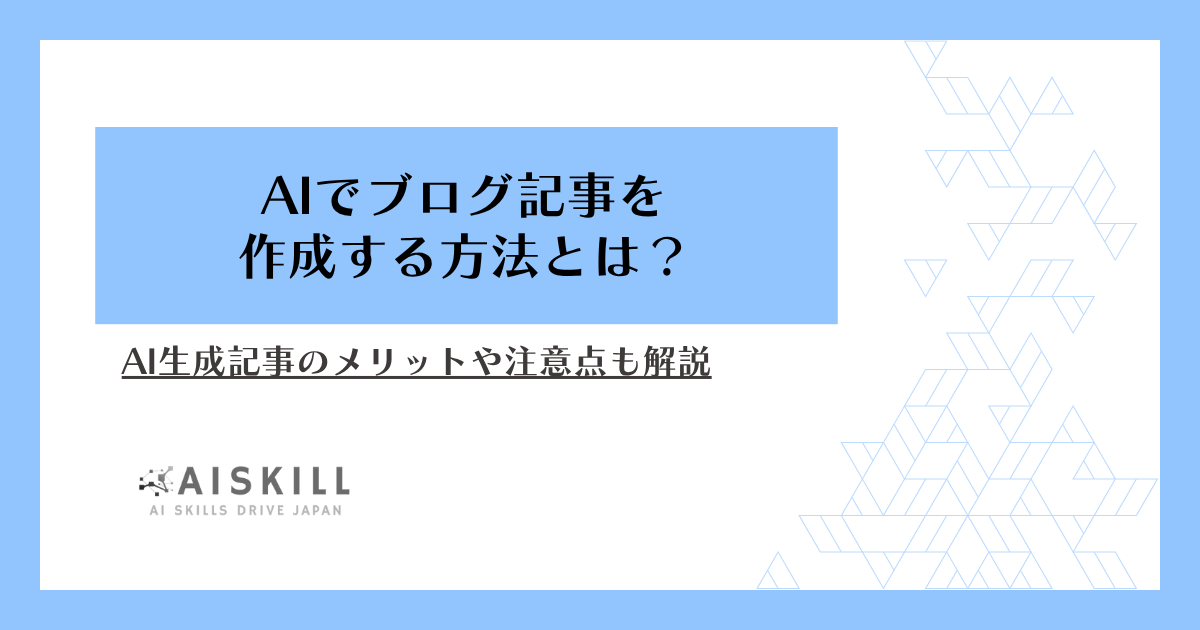
G検定の合格率・合格者数から見る難易度

G検定の難易度を客観的に測る指標として、主催団体が公表しているデータは重要です。
ここでは、G検定の難易度を判断するために、以下の3つの公式データを見ていきます。
- 直近の合格率
- 年代・職種・業種別の合格者傾向
- 合格ラインのおおよその目安
それぞれの内容を具体的に解説します。
直近の合格率
一般社団法人日本ディープラーニング協会(JDLA)が公表しているデータによると、G検定の合格率は、近年おおむね60%台後半から80%前後で推移しています。
IT関連の資格試験において、合格率が60%を超える試験は、難易度としては比較的「標準的」または「やや易しい」レベルに分類されることが多いでしょう。
ただし、受験者の多くが事前にある程度の学習をしていることを考慮すると、決して準備なしで合格できる試験ではないことが分かります。
年代・職種・業種別の合格者傾向
G検定の受験者層は、AIへの関心の高まりとともに多様化しています。
年代別では20代から30代のビジネスパーソンが中心ですが、40代以上の管理職層も増加傾向です。
また、職種別ではソフトウェア開発や情報処理関連のエンジニア層が多いものの、近年は企画、マーケティング、営業といったビジネスサイドの職種や、学生の受験者も増えており、AIリテラシーの裾野が広がっていることがうかがえます。
合格ラインはおおよそ正答率70%前後
G検定の明確な合格ライン(合格基準点)は、公式には発表されていません。
しかし、多くの受験者や資格スクールの分析によると、合格ラインは「正答率70%前後」が目安とされています。
試験問題の難易度によって多少の変動はあると考えられますが、合格を目指す上では、安定して7割以上の正解を目指せるレベルの学習が必要です。
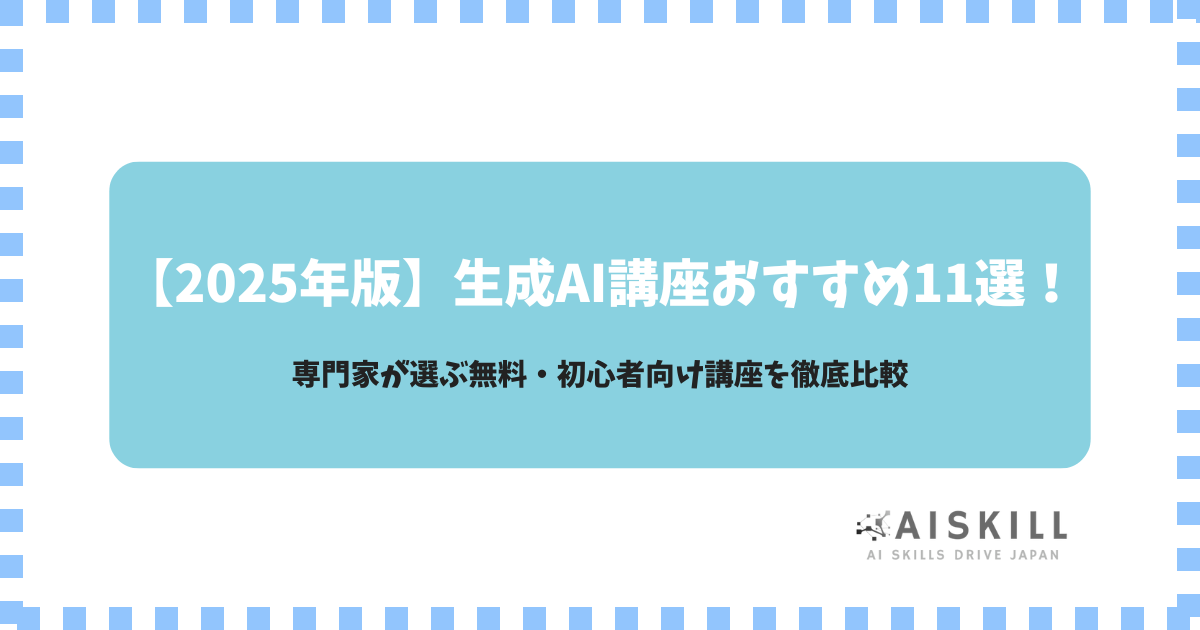
G検定の難易度が高いと言われる4つの理由

G検定の合格率は比較的高めである一方で、受験者からは「難易度が高い」「思ったより難しかった」という声が聞かれることもあります。
その背景には、主に以下の4つの理由が考えられます。
- 出題範囲が非常に広く、AI分野の知識を体系的に問われる
- 問題数が多く、スピードと理解力が求められる
- 数学・統計・アルゴリズムなど専門的な内容を含む
- 合格者の多くが理系・エンジニア層
ここからは、各項目について詳しく見ていきましょう。
出題範囲が非常に広く、AI分野の知識を体系的に問われる
G検定が難しいとされる最大の理由は、その出題範囲の広さです。
AIの歴史や技術的な基礎理論(ディープラーニングの手法など)だけでなく、AIが社会や産業に与える影響、法律、倫理問題まで、非常に広範な知識が問われます。
単なる用語の暗記ではなく、AI分野全体の動向を体系的に理解している必要がある点が、難しさの一因となっています。
問題数が多く、スピードと理解力が求められる
G検定は、120分という試験時間に対して、問題数が約160問と非常に多く設定されています。
単純計算で1問あたり45秒程度で解答する必要があり、問題文を素早く読み解き、即座に判断するスピード感が求められます。
じっくり考えて解く時間が少ないため、知識が曖昧だと時間切れになってしまう可能性が高く、この時間的な制約が難易度を上げています。
数学・統計・アルゴリズムなど専門的な内容を含む
G検定はジェネラリスト向けであり、複雑な計算問題は出題されにくい傾向です。
しかし、シラバスには「AIを支える基礎的な数学・統計の概念」や「ディープラーニングの代表的なアルゴリズム」が含まれます。
文系出身者や数学に苦手意識がある方にとっては、これらの専門用語や概念の理解自体がハードルとなり、難易度が高いと感じる要因になるでしょう。
合格者の多くが理系・エンジニア層
G検定の受験者には、元々ITやソフトウェア開発の知識を持つ理系出身者や現役のエンジニアも多く含まれます。
そうした前提知識のある層を含めた合格率が約60%〜80%であるため、AI初学者やIT分野に馴染みのない方にとっては、相対的により難易度が高く感じられる可能性があります。
類似資格との比較でわかるG検定の難易度レベル

G検定の難易度をより客観的に把握するために、他のAI・IT関連資格と比較してみましょう。
ここでは、特に比較対象とされることが多い「E資格」や「データサイエンティスト検定(DS検定)」との違いを中心に解説します。
E資格やデータサイエンティスト検定との難易度比較
G検定と比較される主なAI関連資格の難易度や特徴は、以下の通りです。
【主なAI・IT関連資格との比較】
| 資格名 | 主催団体 | 対象者像 | 難易度(目安) |
|---|---|---|---|
| G検定 | JDLA | ジェネラリスト(企画・営業職など) | ★★☆☆☆ |
| E資格 | JDLA | エンジニア(実装者) | ★★★★☆ |
| DS検定 | データサイエンティスト協会 | データサイエンティスト(実務者) | ★★★☆☆ |
| 生成AIパスポート | GUGA | ビジネスパーソン全般(生成AI利用者) | ★☆☆☆☆ |
| ITパスポート | IPA | 全社会人(IT初学者) | ★☆☆☆☆ |
E資格は、AIを実装するエンジニア向けの資格であり、Pythonでのプログラミング実装能力や高度な数学の知識が問われるため、難易度はG検定より格段に高くなります。
また、DS検定はデータサイエンティストとしての実務スキルを問うため、G検定より専門的かつ実践的な内容です。
位置づけとしてはAI分野の基礎・入門資格
G検定は、AI分野の資格の中では、AIの仕組みや活用法を学ぶ「基礎・入門資格」と位置づけられます。
ITパスポート試験がIT全般の基礎知識を問うのに対し、G検定は「AI分野」に特化した基礎知識を問う資格です。
一方で、2024年に開始された「生成AIパスポート」は、ChatGPTなどの生成AIの利用スキルに特化しており、G検定よりもさらに間口が広い入門資格といえるでしょう。
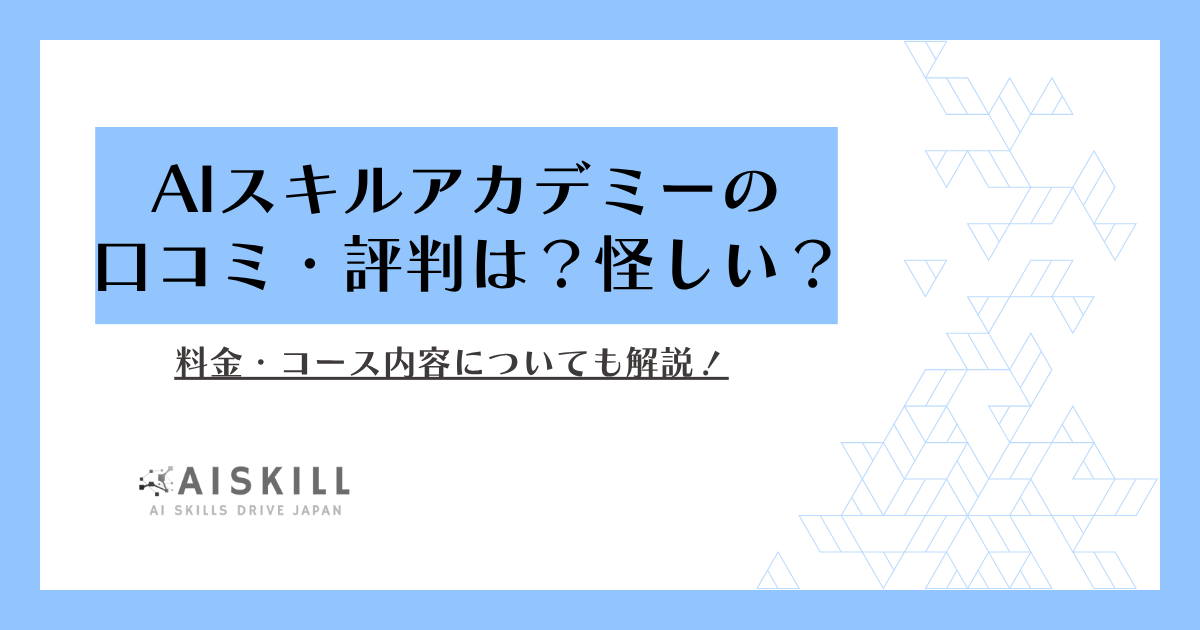
G検定の合格に必要な勉強時間と学習法

G検定の難易度を把握した上で、次に気になるのは「合格までにどれくらいの学習が必要か」という点です。
ここでは、合格に必要な勉強時間の目安と、効率的な学習法について解説します。
G検定合格までの目安は30〜50時間
G検定の合格に必要な勉強時間は、受験者の持つ前提知識によって大きく異なります。
一般的に、AIやITに関する基礎知識が少ない初学者や文系の方の場合、30~50時間程度の学習時間が必要です。
一方で、情報系のバックグラウンドがある方や、日常的にAI関連の情報に触れている方であれば、15~30時間程度の学習で合格水準に達するケースもあります。
効率的な勉強法
G検定の学習を効率的に進めるためには、JDLAが公開しているシラバス(試験範囲)をまず確認しましょう。
その上で、以下の方法で学習を進めるのが一般的です。
- 公式テキストの通読:
まずは公式テキストを一通り読み、試験範囲の全体像と主要な用語を把握します。 - 問題集(公式・市販)の反復:
G検定は問題数が多いため、問題集を繰り返し解き、知識の定着と解答スピードを養います。特に「黒本」と呼ばれる問題集が定番とされています。 - 模擬試験の活用:
試験直前には、本番同様に120分の時間を計って模擬試験を受け、時間配分の感覚を掴んでおくことが合格の鍵となります。
学習手順を考慮すれば、より効率的に知識を把握でき、試験合格までの道のりを短縮できます。
G検定取得で得られるメリット

G検定の難易度や勉強時間を乗り越えて合格することで、ビジネスパーソンにとって多くのメリットが期待できます。
主なメリットは、以下の5点です。
- AI・ディープラーニングを体系的に学べる
- キャリア・転職での評価アップ
- JDLAコミュニティへの参加権
- E資格へのステップアップ
- 副業で稼げる道筋ができる
それぞれのメリットについて具体的に解説します。
AI・ディープラーニングを体系的に学べる
G検定の最大のメリットは、AIやディープラーニングに関する知識を体系的に学べることです。
ニュースやインターネットで断片的に得られる知識とは異なり、AIの歴史から最新技術、法律・倫理面までを網羅的に学習することで、ビジネスにおけるAI活用の強固な土台を築くことができます。
キャリア・転職での評価アップ
AIの活用はあらゆる業界で急務となっており、AIリテラシーを持つ人材の需要は高まっています。
G検定の合格証は、AIに関する基礎知識を客観的に証明するものとなり、社内でのキャリアアップや、転職活動における評価向上につながる可能性があるため、メリットといえるでしょう。
ただし、2025年の転職市場では、G検定の認知拡大とともに保有者も増加しているので、資格を保有している旨のアピールで終わらないよう注意しましょう。
G検定を取得する過程で得た知識を、実際の業務でどのように生かせるのか、これまで培った経験やスキルを交えながら示すことが大切です。
JDLAコミュニティへの参加権
G検定に合格すると、JDLAが運営する合格者限定のコミュニティ「CDLE(Community of Deep Learning Evangelists)」に参加する権利が得られます。
このコミュニティでは、AIに関する最新情報の交換や、業界を超えた合格者同士のネットワーキングが可能となり、自身の知見をさらに深める場として活用できます。
CDLEは、10万人を超える規模のコミュニティであることから、参加できるのみでも大きなメリットです。
E資格へのステップアップ
G検定でジェネラリストとしての基礎知識を固めた後、さらにAIの実装スキルを身につけたいと考えた場合、エンジニア向けの「E資格」へのステップアップが視野に入ります。
G検定の学習内容はE資格の基礎とも重なる部分があり、スムーズな学習移行が期待できるでしょう。
副業で稼げる道筋ができる
G検定で得られる「体系的な知識」は、AIを安全かつ効果的に活用するための基盤となります。
ただし、知識があるだけでは、ChatGPTなどを活用した記事作成や資料作成といった副業案件をこなすのは難しいでしょう。
G検定の知識に加え、「AIスキルアカデミー」のようなスクールで実践的なプロンプト設計や実務ノウハウを学ぶことで、知識とスキルが結びつき、初めてAIを活用した副業などで収益を上げる道筋が見えてきます。
G検定に関するよくある質問

最後に、G検定の難易度や受験に関して、AIスキルアカデミーにも多く寄せられる質問にお答えします。
- G検定の受験料は?
- G検定はどこで受けられる?
- G検定に合格しないでE資格を受験することは可能?
それぞれの質問について確認していきましょう。
G検定の受験料は?
G検定の受験料は、一般の方が13,200円(税込)、学生の方が5,500円(税込)です。
過去にG検定を受験したことがある場合、再受験割引が適用される制度もあります。
詳細な料金体系や割引制度については、JDLAの公式サイトで最新情報をご確認ください。
G検定はどこで受けられる?
G検定は、IBT(Internet-Based Testing)方式を採用しており、特定の試験会場はありません。
インターネット環境が整った場所であれば、受験期間中にご自身のPCを使用して、自宅や職場など、どこからでも受験することが可能です。
ただし、定期的に開催される会場試験の場合は、指定の試験場にて受験できます。
G検定に合格しないでE資格を受験することは可能?
はい、G検定に合格していなくてもE資格を受験することは可能です。
E資格の受験資格は、「JDLA認定プログラム」と呼ばれる専門講座を試験日の過去2年以内に修了していることです。
G検定の合格はE資格の受験要件ではありませんが、E資格の学習内容を理解する上で、G検定レベルの基礎知識は役立つでしょう。
まとめ

この記事では、G検定(ジェネラリスト検定)の難易度について、最新の合格率、必要な勉強時間、E資格など他資格との比較、そして難易度が高いと言われる理由を解説しました。
G検定はAI分野の基礎・入門資格と位置づけられますが、合格率は約60%~80%、勉強時間も30時間以上が目安となり、決して簡単ではありません。
しかし、文系の方や数学が苦手な方でも、シラバスに沿った効率的な学習で十分に合格が可能です。
本記事で解説した学習時間や効率的な手順を参考にして、G検定取得を目指しましょう。